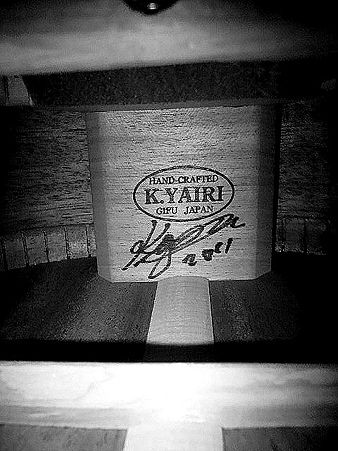×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
引退のがけっぷちに追い込まれた“プロボクシング界の中年の星”西沢ヨシノリ(41)=ヨネクラ=が31日、週明けにも出される見込みの日本ボクシングコミッション(JBC)の引退勧告に「素直に従う」と受け入れる意向を示した。
西沢は、1月30日の東洋太平洋ライトヘビー級王座の初防衛戦でヒース・ステントン(オーストラリア)に0-3の大差判定で負けて王座陥落。「負ければ引退」などの条件付き特別措置で37歳引退制を免れていたが、惨敗で引退は不可避。一方で「再戦したい気持ちはある」と未練も口にした。海外で活動の場を模索することも考えられるが、JBCの安河内(やすこうち)剛事務局長は「日本の判断は諸外国にも反映されるだろう」という。同事務局は、週明けにも今後の結論を出す意向だ。
中年の星が引退の崖っ縁に追い込まれた。ボクシングの東洋太平洋ライトヘビー級タイトルマッチ12回戦が30日、東京・後楽園ホールで行われ、11日に41歳の誕生日を迎えたばかりの王者・西沢ヨシノリ(ヨネクラ)は、挑戦者の同級1位ヒース・ステントン(31=オーストラリア)に0―3の判定で敗れ、初防衛に失敗した。最大で8ポイント差がつく大差の判定でいいところなく敗れたことで、特例による現役続行を許可されてきた西沢に、日本ボクシングコミッション(JBC)が引退を勧告する可能性が高まった。
西沢には王座陥落よりも、敗戦の事実が重くのしかかった。41歳19日。10歳年下のステントンに開始から左フックを浴び続けた。顔面は赤みを帯び、5回には相手の左ジャブで左目尻をカット。終盤には完全にスタミナが切れ、満員の2200人の観客の西沢コールも届かなかった。「判定は2―1で取ったかと思った。勝って次のステップに行こうと思っていたのに、今は何も考えられない」。そうつぶやいた西沢は唇をかんだ。
05年10月のミトレフスキー(オーストラリア)戦で顔面が変形するほど腫れ上がり、10回負傷判定負けをした。当時39歳。37歳定年制の中、元王者の実績から試合を許されたが、JBCから現役続行に待ったがかけられた。話し合いの末、試合内容と結果で判断する引退勧告を、その後は受け入れる条件で認められた現役続行だった。
特例での現役は「勝つこと」しか許されない。昨年11月、背水で臨んだ東洋太平洋ライトヘビー級王座決定戦で見事に1回KO勝ちし、生き残った。40歳でのタイトル奪取は国内最年長という勲章つきだった。20歳の86年10月にプロデビュー。初タイトルとなった日本ミドル級王者に就いたのが31歳で、念願の世界初挑戦は38歳。コツコツと目標に向かう姿に多くの人が共感した。
だが、この敗戦で今後の進退はJBCに一任されることになった。安河内事務局長は「ドクターを交えて試合内容を慎重に検討したい。今回の負けは大きな判断材料になる」と引退を示唆した。「とりあえずゆっくり休みたい。負けたのでこれ以上言うことはない」と話して会場を後にした西沢の運命の“判定”は、今週末にも下される。(c)Yahoo!
11回、ボディーへのパンチに顔をゆがめる西沢
徳島市の山の急斜面で昨年11月に救出された「崖(がけ)っぷち犬」の飼い主を探す会が28日、徳島県神山町の県動物愛護管理センターであり、抽選で同県つるぎ町半田の主婦、馬木(うまき)カズ子さん(66)に引き取られた。馬木さんは「早く一緒に散歩できるようになりたい」と話しており、帰宅途中、広島県福山市に住む小学3年の孫娘と電話で相談して「リンリン」と名付けた。会では、くじが外れた小学生が泣き出す場面もあった。
生後8カ月程度とみられる子犬は救出から2カ月で体重が1.6キロ増え、人の手からえさをもらうなど慣れてきた。当初、全国の109人から電話などで引き取りの申し出があったが、この日の抽選にはセンターへ来なければならず、県外の2人を含む11人だけが参加した。
一方、この子犬の4日前に同じ斜面で保護された、体形などから姉妹とみられる別の犬もセンターで保護されているが、引き取り手は見つかっていない。センターでは今後も飼い主を探すという。【加藤明子】
徳島市の眉山の崩落防止コンクリート壁のくぼみに迷い込んだ1匹の子犬に、17人のレスキュー隊員が出動した大がかりな救出作戦の模様が全国中継された“がけっぷち犬騒動”から2カ月。保護された子犬の譲渡会が28日、徳島県動物愛護管理センター(同県神山町阿野)で開かれ、飼い主が決まる。(c)SankeiWEB
人にもなれ、すっかり元気になったがけっぷち犬
=徳島県神山町の県動物愛護管理センター
この犬は、当時生後6カ月の雑種の雌。当初は飼育室の片隅でおびえきっていたが、今ではすっかり人にもなれ、先に救出された姉妹とみられる犬と一緒に元気に遊んでいる。
思い起こせば、救出劇はハラハラ、ドキドキの連続だった。がけのくぼみは約50メートルの高さ。消防署のレスキュー隊員が犬の下に保護ネットを張り、徐々に近づいていく。最後は犬を保護ネットの中にダイブさせ、救出に成功した。
救出の一部始終は全国にテレビで生中継され、その直後から同センターの電話は鳴りっぱなし。そのほとんどが犬の引き取り希望や問い合わせで、件数は今月26日現在で109件に上っている。
引き取りの理由は、「ひどい目に遭ってかわいそう」「幸せにしてやりたい」「以前飼っていた犬に似ている」などのほか、「ラッキーさにあやかりたい」「店の看板犬にしたい」といったものまで、さまざまだ。
同センターで平成17年度に殺処分された犬は約4500匹、今年度は12月末で約3200匹に上っている。がけっぷち犬のように全国的に注目されたため助かった幸運な犬がいる一方、人知れず殺処分される犬は多い。
同センターでは、騒動後も1カ月に約300匹の割合で処分が続いているという。
同センターの山根泰典・事業係長は「できればみんな助けてやりたいが…。ただ、この救出された犬のように引き取り手があり、訓練しだいで人になれる可能性がある以上、あえて処分する必要はない」と話す。
譲渡会は午後1時から。倍率は高く、「厳しい抽選会」となりそうだ。
(2007/01/27 15:38)
金融庁が三菱東京UFJ銀行に対し、一部業務停止命令などの行政処分を出す方針を固めたことが二十七日分かった。業務上横領などで実刑判決を受けた人物が理事長を務めていた財団法人に長年融資し、関与してきたことを問題視している。処分は、不正の舞台となった大阪地区で新規の企業向け貸し出しを数カ月間停止する案が有力とみられる。
問題にするのは、三菱東京UFJ銀行の前身、旧三和銀行時代の一九八〇年代半ばから、財団法人「飛鳥会」(大阪市)の元理事長側に貸し付けてきた数十億円規模の融資で、その大半は焦げ付いている。行員を派遣して経理業務もさせていた。同会の小西邦彦元理事長は今月二十四日、業務上横領と詐欺の両罪で懲役六年の判決を受けた。
金融庁は公益性が高い大手金融機関がこうした不正取引を、東京三菱銀とUFJ銀行(旧三和銀行・旧東海銀行)が合併した後も続けてきた内部管理体制の不備を重視。法令順守を徹底させることが必要と判断したもようだ。
貸し出し停止処分が発動されれば、現時点で同銀行と取引がない企業は処分期間中、融資を受けられなくなる。
<メモ>飛鳥会事件 同和地区の福祉向上を目的として設立された財団法人「飛鳥会」(大阪市東淀川区)の元理事長が同会を私物化し、約1億3000万円を着服した業務上横領などの罪で懲役6年の実刑判決を受けた事件。
旧三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)淡路支店の次長も業務上横領ほう助容疑で逮捕され、起訴猶予となった。
約百七十匹の犬・猫を飼育していた八戸市の犬の繁殖業者(ブリーダー)が経営難に陥り、二十六日までに県へ動物取扱業者の廃業届を出した。県によると、あと十日程度でえさがなくなる状況という。病気など健康状態の良くない犬もおり、県は二十七日から、青森、八戸の両市で無料譲渡会を開く。
この業者は、今年六月から義務付けられる飼育要件のうち施設基準などの一部を満たしておらず、県が昨年、口頭で改善指導していた。ペットブームに乗じ、他県では無責任な業者による劣悪な環境下の飼育が問題になった事例もあり、本県でも飼育の在り方に一石を投じそうだ。
県動物愛護センターによると、業者はインターネットや口コミで犬を販売していた。飼育困難になり、現在、皮膚病や腫瘍(しゅよう)を患っていたり、警戒心の強い犬もいるという。
県動物愛護協会が支援を決定し、協力する形で譲渡会を開くことにした同センターは「繁殖用のほか持ち込まれた犬や猫を引き取るうち、スタッフ数に対して増え過ぎてしまったようだ。虐待など悪質な事例ではないが飼育状況に不適切な面もあった」と説明。「病気でも動物病院の受診で治癒したり、すむ環境を変えれば改善する。譲渡会で状態を確認し、気に入れば救ってほしい」と呼び掛けている。
犬はミニチュアダックスフント、チワワ、ビーグルなどの人気犬種も含まれている。センターに順次搬送し、体を洗ってから譲渡会に臨む。譲渡希望者には、飼育環境や家族状況について、センター職員が面談する。狂犬病予防法に基づく犬の登録や、狂犬病予防注射、センター講習会受講が義務付けられる。
譲渡会は次の通り。いずれも午後一時から。
▽県動物愛護センター=27日、28日、2月3日
▽ピアドゥ(八戸市)=2月4日
▽マエダストア西バイパス店(青森市)=2月4日
【ジュネーブ=渡辺覚】国際労働機関(ILO)が25日発表した世界の雇用情勢に関する年次報告によると、2006年末時点の世界全体の失業者は、前年を約50万人上回る推計約1億9520万人にのぼり、過去最悪を記録した。
失業率は、前年から0・1ポイント改善したものの、6・3%の記録的な水準で高止まり。報告は「世界各地の経済成長が雇用情勢の改善につながっていない」と指摘し、失業者数・失業率ともに、07年も同様の水準で推移すると予測している。
また、若年層(15~24歳)の06年の就労率は46・8%。高学歴化による就労年齢の上昇に加え、各国で仕事に就けない若者が増加している事実も背景にあり、特に先進諸国では、若年層の失業率が、25歳以上の層の2倍以上に上っていると指摘。「若年層の労働力を活用できないのは、社会の潜在的損失だ」と各国政府に警告した。
政府の教育再生会議(野依良治座長)がまとめた第1次報告最終案に、今後の検討課題として「週5日制の見直し」が盛り込まれていることが18日明らかになった。そげな、
再生会議が目指す「ゆとり教育の見直し」や「授業時間数の10%増加」の具体策として挙げたもので、実現すれば約15年ぶりの政策転換となる。同会議は最終案を19日の合同分科会で議論した後、24日の総会で正式決定して安倍首相に提出する。
週5日制は92年から月1回、95年から月2回と段階的に試行され、2002年度に公立学校で完全実施された。子供が家庭や地域で過ごす時間を増やし、考える力や生きる力をはぐくむのが目的だったが、授業時間が削減されたことで、学力低下の一因とも批判されてきた。
最終更新:1月19日3時7分
読売新聞
期限切れ原料使用で社長が陳謝子どもが腹痛を起こす可能性を認識してたわけや。
【ライブドア・ニュース 2007年01月11日】- 大手菓子メーカーの不二家<2211>は11日、埼玉工場(同県新座市)で消費期限切れの牛乳をシュークリームの製造に使用していた問題を受け、品質管理の徹底が図れるまで、全国5カ所の洋菓子工場の操業を停止し、全国約900カ所のチェーン店やレストランでの洋菓子販売を休止すると発表した。
同日、東京都中央区の同本社で開いた記者会見で藤井林太郎社長は、「品質管理体制が不十分で、関係各所にご迷惑をおかけした。誠に申し訳ございません」と陳謝した。
その上で、埼玉工場で昨年10月から11月かけ、消費期限切れ牛乳を計8回使用し、少なくとも2000個のシュークリームを製造したことを認めた。消費期限切れの牛乳の使用については、原料廃棄に関する内規の内容が不十分であった点と、従業員への周知の不徹底が原因と説明。問題に関わった従業員は聞き取り調査に対し、「技術的に問題ないと思った。味を見て使っていた」などと話しているという。
さらに、同工場で新たに発覚した不適切な製品製造を公表。◆賞味期限切れりんごの加工品を計4回使用しアップルパイを製造した◆プリンの消費期限を社内基準より1日長く表示していた◆食品衛生法の基準値の約10倍の細菌が検出された洋菓子「シューロール」を出荷していた――として、これらの製品を新潟や福島など1都9県に出荷した可能性があることを明らかにした。健康被害の報告はないというが、幼児などが製品を食べると腹痛を起こす場合があるという。埼玉のほか北海道、栃木、大阪、佐賀の工場を、安全性が確認されるまで操業停止とする。
今回公表された問題は、昨秋の社内会議で報告されていたが、事実関係の公表までに2カ月以上かかった。公表が遅れたことについて藤井社長は、「考え方が甘かった。対応策に気をとられ、(公表することには)意識が及ばなかった」と責任を認めた。
また、同会議の中で「(問題を)マスコミに知られたら、雪印の二の舞になりかねない」という文書が幹部に配布されていたことも明らかになった。
同社は今後、第3者を入れた社内調査を進めるとともに製造マニュアルの徹底や改訂などを実施し、原因究明と再発防止に取り組むとした。洋菓子販売の再開時期については「生産を開始するまでに最低でも1週間はかかる」(藤井社長)との見方を示した。経営責任については、「社会的な信頼回復を第一義に考えたい」と述べた。【了】
18日午前1時40分ごろ、神戸市長田区御屋敷通3のコンビニエンスストアから、少女が化粧品を盗んで逃げたと長田署に通報があった。同署員は、近くのマンションで同区内の無職少女(15)を発見。同署へ任意同行を求めると、少女は「何で行かなあかんの」と言って抵抗。パトカーの後部ガラスを2回頭突きして割ったため、器物損壊容疑で現行犯逮捕した。少女は頭部に軽傷を負った。スゲっ
同署は「パトカーのリアの窓ガラスは丈夫にできているので、簡単に割れるものではない」と驚いている。【岩嶋悟】
〔神戸版〕
12月19日朝刊
【ボストン(米マサチューセッツ州)=田中富士雄】米大リーグのレッドソックスは14日(日本時間15日)、ポスティングシステム(入札制度)で独占交渉権を獲得した松坂大輔投手(26)と、6年契約を結んだと発表した。
年俸は明らかにされていないが、米メディアの報道によると、総額5200万ドル(約61億1000万円)。
球団本拠地のフェンウェイパークで記者会見が開かれ、松坂は背番号「18」のユニホームを披露。「うれしいし、興奮している。夢見るのではなく、目標として信じてきたから、ここにいるんだと思う。先発投手陣に入れるように頑張る」と喜びを語った。
松坂は9日にロサンゼルス入りし、レッドソックスとの最終交渉をスタート。当初は契約年数、年俸とも両者に大きな隔たりがあり、一時は決裂を予想する声も上がったが、同制度で定められた交渉期限の15日午前0時までに歩み寄った。
中国で急速に広がるペットブームに乗じ、犬の販売業者が暴利をむさぼっている実態が明らかになっている。北京・上海・広州で調査を行ったところ、犬の価格が仕入れ価格の30~50倍で売られていることが判明。犬市場が規制なしに利益を得られる“無法地帯”と化している。背景には、過熱するペットブームに行政側の管理が追いついていないこともあり、ペット市場全体の整備を求める声も上がっている。
■1匹販売で10万元の利益
北京市最大のペット用犬マーケット・愛斯達名犬交易市場によると、一般市民は各犬種の相場に疎いため、大部分が販売業者の言い値で購入していく傾向にあるという。青海省では1,000元(約1万5,000円)前後で購入できる生後30日程度のチベタン・マスティフが、北京市では3万~5万元で売れるという。
同市で最も人気がある1,000~2万元レベルのペット犬でも、繁殖・仕入れコストは1匹わずか数百元程度が相場。同交易市場に店舗を構える韓国籍業者は「30万~40万元の高値で販売されるチャウチャウ犬では、1匹販売することで10万元の利益を得ることも可能だ」と話し、“うま味”のある商売であることを示唆した。
広州市物価局の関係者は「現在ペット市場の価格設定は業者の自由。行政が法外な利益獲得に関して干渉することはできない状況」と話しており、行政としては静観の構えだ。
■繁殖場の9割無許可
インターネットサイトの中国寵物(ペット)市場網によると、北京市だけで今年7月時点にペット登録されている犬は50万匹余りに上り、年間8%ペースで増加している。
今年8月末に、北京市獣医衛生監督所が犬類繁殖場に対して行った調査では、同市の繁殖場は計125カ所に上ることが判明。しかし、業界関係者は、50匹以上の犬を飼育している繁殖場は300カ所以上、さらに小規模なところを加えると、実際に合法的に営業している繁殖場は全体のわずか10%前後しかないと指摘する。およそ9割の繁殖場が、行政の管理の目を免れていると言え、狂犬病被害が関心を集める昨今では、衛生管理などで市民に不安を与える大きな要因となりそうだ。
■ぜいたく品税の対象に?
愛斯達名犬交易市場には100軒以上のペットショップが並ぶ。多い日で1日400~500匹の犬が売れており、同市場で最高額のチャウチャウ犬は40万元という高値が付いている。
この盛況ぶりに反して、ショップ1軒が支払わなければならない各種税金は合わせてわずか200元。しかも、現在は交易市場側がすべて立て替えているため、業者の利益は巨額。業者の一人は「政府は“犬産業”をまったく一つの業界とみなして管理していない」と指摘する。
中国人民大学社会学部の洪大用教授は、「政府は犬の繁殖、販売に対しても、化粧品などに適用されている『ぜいたく品税』を徴収すべき」と強調。犬産業の暴利を抑制すれば、繁殖場、販売業者は減少する。一方で、飼育コストが上昇すれば、気軽にペットを購入する人も減り、狂犬病感染などの恐れを持つ野良犬や捨て犬も減少するという理論だ。
広東省消費者委員会の関係者は、「政府は拡大し続けるペット市場をもっと重視し、公安、商業、繁殖、衛生など各関連部門がそれぞれの責任を明確化してヤミ市場や安全といった問題を解決すべき」と主張する。
■ペット経済150億?
美容室、訓練所、ペットホテル、写真撮影など、ペット関連市場の裾野は広く、中国のペット関連産業は少なくとも150億元規模に達すると推測されている。
2001年の北京市を例に上げると、輸入物ペットフードの売上高は2億元に上り、前年比130%も増加。その後もブームの過熱に伴い、各関連商品の需要は伸び続けている。ペット用医療機関や美容院などの技術は、先進国レベルとの差が依然大きく、残された市場は巨大だ。
市民の懐具合とともに、急速に膨らんだペット市場。一大産業として健全な発展を遂げるかどうか。行政による市場管理の徹底が成功のカギを握っていると言える。【北京・新田理恵】<全国>
(c)asahi.com
敷地400平方メートル以上の住宅しか
建設できない条例改正案が検討されている芦屋市六麓荘町(手前)。
屋敷林が多いのが分かる
=11月30日午後、同市で、本社ヘリから
日本屈指の高級住宅街とされる兵庫県芦屋市六麓荘(ろくろくそう)町(252世帯)で「敷地400平方メートル以上の一戸建て」しか新築できないようにする条例改正案を4日、市が議会に提案した。相続税を払えないなどの理由で土地を手放す地主が相次ぎ、住民が求める「閑静な住宅街」の維持が瀬戸際にあるためだ。高級感を最大の特徴とする芦屋ブランドを守りたい市が、住民の要望を受け入れた形で、全国でも異例の「豪邸しか建てられない街」が生まれることになりそうだ。
六麓荘町の住民は、開発当初から町内会独自の協定を設け、高級住宅街の維持に努めてきた。協定では、建物は一戸建ての個人宅に限り、新築と増改築には町内会の承認が必要▽敷地は400平方メートル以上▽町内での営業行為は一切禁止する――などを制定。このため町内にマンションや商店はまったくない。
しかし、バブル経済の崩壊後、資金調達のために土地を売ったり、相続税を払えなくなって土地を物納したりする住民が続出。町内の物件の約7割を手がけてきたという「芦屋不動産」(芦屋市)の深見徹五郎会長によると、この15年で約50件の土地が分割されるなどして手放された。土地を差し押さえられ、競売にかけられた例もあったという。
住民の危機感が一気に高まったのが03年8月、甲子園球場のグラウンドの約半分にあたる約7400平方メートルの土地が一度に売りに出された時だ。バブル期は3.3平方メートル(1坪)あたり700万円した土地が約100万円まで下がり、協定に反して老人ホームを建てる計画が持ち上がった。住民たちの反対で一戸建て用地として分割売却されたが、住民たちは04年12月にまちづくり協議会を結成。市に条例づくりを働きかけてきた。
市が提案したのは地区ごとの建ぺい率などを定めた「建築物の制限に関する条例」の改正案で、対象地域は、六麓荘町の全体約37.7ヘクタール。400平方メートル以上の敷地への一戸建て住宅しか新築を認めない▽建物の高さは10メートル以下にする――2点が柱で、町内会の協定を踏襲した。同市建築指導課は「高級住宅地としての芦屋ブランドを守りたいという意思が住民と一致した」と説明している。
まちづくり協議会会長で、大阪土地協会理事長でもある武村泰太郎さん(77)は「土地の利用方法を条例で制限すれば価値が下がるという意見もあったが、住環境を保つための規制なのでそうはならないだろう」と話す。
関東では東京都世田谷区が、同区玉川田園調布で都市計画法に基づく地区計画で敷地を160平方メートル以上と130平方メートル以上の2種類に制限している。同区成城では自治会が「成城憲章」を定めて250平方メートルを標準的な敷地とし、相続税対策で土地を分割する際は1件の広さを125平方メートル以上とするよう定めている。
国土交通省市街地建築課の担当者は「一戸建ての敷地面積にゆとりを持たせる規制は他地域にもあるが、200平方メートル程度を確保する場合が一般的で、400平方メートル以上は聞いたことがない」としている。
<芦屋市六麓荘町> 1928(昭和3)年、大阪の財界人らが設立した「株式会社六麓荘」が、香港の白人専用街区をモデルに開発したとされる。景観に配慮して電線を地下に埋めたり、治安維持のため町内会館に駐在所を設けたりと先進的な街づくりを進めてきた。六甲山系のおいしい水を飲むために自前で浄水場をつくったこともある。町内会の入会金は50万円。(c)asahi.com