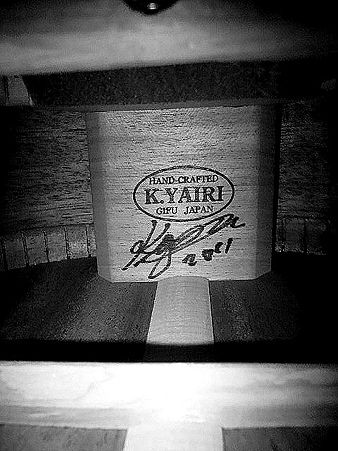×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
(c)asahi.com
(c)asahi.com
(c)asahi.com
2006年05月29日
長年、いろいろなタイプの同僚の教授と接してきてわかったことがあります。「人間は文系人間と理系人間に分類できるのではないか」ということです。
最近の大学はこれまでの理系や文系にとらわれない新しいジャンルの学部が新設されています。
私の大学には例えば、メディア学部といって創造的な視野をもった社会人を作る目的で、文系や理系のほか、エンターテインメント系の学問も同時に学べる学部があります。
その結果、大学の名前は工科大でも多くの文系の先生が理系の先生とともに過ごしています。長年、大学の教員生活を続けてみて、それぞれ共通の性格みたいなものが見えてきました。
例えば、敷地内にテニスコートを作る計画が出されます。私のような理系人間は「テニスをする場所が増えていいな。いつまでにできるのかな」と考えます。しかし、「キャンパスの美観を損ねないか」という先生が出てきます。たいてい文系人間の人たちです。
新校舎を建設する話が持ち上がると、理系人間は「どういうふうに研究者の勝手がいい構造にしようか」と考えます。文系の人たちは「自然環境を破壊しないように樹木の移植を考えたらどうか」となるわけです。
理系人間は「まずは結論ありき」だと思いますが、文系人間は「議論をつくして結論を出すべきで、最初から結論があるのはおかしい」ということなのかもしれません。
もちろんこの場合、単純に理工学部の人は「理系人間」、法学や経済、文学の人は「文系人間」とはならないでしょう。
理系人間と文系人間は私の専門のバイオテクノロジーの分野からすると、それぞれ人間の「左脳」と「右脳」のどちらが発達しているかにかかわっていると思います。
本来「左脳」は「理論脳」とも言われ、知識をつめこむ「デジタル脳」です。これに対し、「右脳」は「芸術脳」で感覚を重視する「アナログ脳」なんです。
私は学会で地方に行くと、地元のラーメンをよく食べます。最近、私の大学の地元、八王子にも独自のラーメンがあると聞いて驚きました。
基本はしょうゆ味で、タマネギなどを刻んで味付けされているそうです。その八王子ラーメンを紹介するため、学生や教員たちが最近、地元のラーメン屋さんを紹介した「ラーメンマップ」を作りました。
そういう作業では、値段などのデータベース化は理系人間、味を調べて地図のデザインを考えるのは文系人間が力を発揮することになります。
日本は高度経済成長期には「理系人間」が力を発揮してきました。これからは「文系人間」の協力がなければ本当の大学の姿はもとより先進国にはなりえないでしょう。 (東京工科大バイオニクス学部教授)
【軽部征夫教授のキャンパスブログ】
愛犬のしつけに悩む飼い主に、芦屋動物愛護協会が定期的に開く一日教室が人気を呼んでいる。インストラクターを招き、二時間にわたって調教。「無駄ぼえが減った」「暴れなくなったので散歩しやすくなった」と、気性の荒い犬が従順な〝優等生〟に。リピーターも増え、ここ数回は定員の倍の応募があるという。 (鎌田倫子)
根強いペットブーム。芦屋市でペットとして飼われている犬の登録数はここ数年、毎年二百匹ずつ増え、現在約三千六百匹。一方で、飼い主のマナー違反や愛犬に十分なしつけができていないことがここ数年表面化。協会には「子どもに飛びかかりそう」「ほえられて怖い」「かみつくくせがある」などの苦情や飼い主の悩みが寄せられていた。
このため同協会は三年前から犬のしつけ教室を開催。県動物愛護センター(尼崎市)でしつけ教室を開くボランティア団体スタッフで、指導歴約十年間の山岸恵美子さん(49)を、毎回講師に迎えている。
飼い主とのアイコンタクトに始まり、名前を呼んだら飼い主の元へ戻る「呼び込み」、飼い主の足に沿うように歩く訓練などを実施。課題をクリアできたら即座に愛犬をほめる「三秒ルール」を徹底させるなど、飼い主にもしつけのこつを助言している。
夫婦で愛犬チェリー(オス、六歳)と初めて参加した同市朝日ケ丘町の石黒喜佐江さん(75)は「チェリーは以前は夫の言うことしか聞かなかったのですが、私の手からエサを食べるようになりました」とうれしそう。
同協会は「しつけをしていない犬はドッグカフェでも迷惑。人間の犬への接し方が変わると、犬は驚くほど変わるもの。基本を学んで、家で少しずつ教えてほしい」としている。しつけ教室は随時開催。市役所経済課内の協会TEL0797・38・2033(c)神戸新聞
しつけ教室で愛犬の指導にあたるスタッフ
=芦屋市劔谷、芦屋市霊園
あ・・・(c)BCN
バンダイ(上野和典代表取締役社長)は5月30日、アース製薬(大塚達也代表取締役社長)と共同で企画した携帯用虫よけ器、「おそとでノーマット 仮面ライダーカブト」を6月1日に3万6000個限定で発売すると発表した。価格は1 785円。
子ども向けテレビ番組「仮面ライダーカブト」に登場する仮面ライダーのベルトをモチーフにした、コンセント不要の電池式携帯虫よけ器で、煙が出ないのが特徴。本体に電池とカートリッジをセットしスイッチを入れるとファンが回り、カートリッジに浸透させた薬剤が拡散、虫よけ効果を発揮する。カートリッジは無香料タイプ。1枚で約2週間効果が持続する。
「仮面ライダーカブト」の変身ベルトをモチーフにしたデザインで、裏面のフックをズボンのウエスト部分などに差し込んで使用できる。同社では、「ライダー気分を味わいながら、いやな虫をシャットアウト。キャンプやアウトドアなど夏のレジャーで便利にご使用いただけます」としている。
本体、カートリッジ1枚、単3乾電池2本が付属し、カートリッジの交換時期を知らせるパイロットランプも備えた。つめかえカートリッジはアース製薬の「蚊に効くおそとでノーマットつめかえ」が使用できる。
記事提供:WebBCN (BCN)
日本人男性の精子数は、フィンランドの男性の精子数の約3分の2しかないなど、調査した欧州4か国・地域よりも少ないことが、日欧の国際共同研究でわかり、英専門誌と日本医師会誌5月号に発表した。
環境ホルモンが生殖能力にどう影響するか調べるのが目的。精巣がんが増えているデンマークの研究者が提唱し、日本から聖マリアンナ医大の岩本晃明教授(泌尿器科)らが参加した。神奈川県内の病院を訪れた、20~44歳の日本人男性324人(平均年齢32.5歳)の精液を採取した。
年齢などの条件は各国でそろえ、禁欲期間の長さの違いによる影響が出ないよう補正して、各国男性の精子数を統計的に比較した。
漢字が書けずに恥ずかしい思いをしたことはありませんか?
会議の時、ホワイトボードに簡単な漢字が書けず、ひらがなになってしまった……。領収書を切るときに相手方の名前を書くことができなかった……。「だきょう」が書けずに「だ協」になったり、「やなぎさわ」が書けずに「やなぎ沢」になったりでは、面目丸つぶれです。
パソコンに頼るあまり、手で文字を書く習慣が薄れている現在、漢字が書けなくなっている大人が増殖しています。運動が不足すると体力が落ちるように、書く機会が減れば自然と漢字を書く力も衰えるのです。そして、カタチはなんとなく分かるんだけど……、ここまで出てるんだけど……と苦しい思いをすることになります。
本書では小学校で習うものから、日常的に使うものまで、度忘れしてしまいそうな漢字を400集めました。一度「そうそう、こうだった」と思い出して書けば、手が覚えるもの。この機会に漢字の勉強をしなおしてみてはいかがですか?
いえ、ちゃいます。と言って全く通じなかった記憶あり。
えと~~~、えと~~~~、
チョンと書いて、チョンと書いて、
チョンチョンで~~す。


これは記事と違ってバックナンバーが残るので、引用なしだっ。なるほどねぇ・・・
言葉が、で、でない・・・
75㎡・・・
ギャっ
苔も奥が深い・・・オヨヨ・・・
植え付けと管理、見たかったのやが、
工事中・・・
アイルランド・小島瑞生 ガーデンだって家の一部だ
春が来た! 冬眠していた小動物たちの動きが活発になるのと同時に、アイルランドでもガーデニングが活発になる。それまでは街も家々の庭も寒々としていたが、これからはみんなこぞってガーデニング用の一式を買い込み、大仕事にかかるのだ。
この時期になると、スーパーなどでいろいろな種類の花の種や苗などが売り出される。チューリップなどの球根を始め、カラフルな可愛い花が咲く種のセット、野草の花の種、そしてレタスやパプリカといった菜園用の種などである。様々なサイズの植木鉢ももちろんある。軒下からぶら下げるタイプの鉢は花がたくさん咲くと本当に美しく、ヨーロッパらしさを見せてくれる。
ガーデニングに欠かせないシャベルやくわ、くま手といった「ガーデニングセット」も安価で手に入る。種類がありすぎて、どうやって使うのか分からないものもかなりある。てっきりプロ用のガーデニング道具かと思ったが「ガーデニング初心者用」とあった。え、そうなの……?
花が咲き乱れる5月以降に近所の家の庭を見て回ると楽しい。こちらでは道行く人に花や植物がよく見えるように植えてあるので散歩をするだけで目の保養になる。まるで花いっぱいの庭の品評会のようである。
春になると、もう一つ仕事が増える。庭の芝刈りだ。冬場じっとしていた庭の芝生と雑草は、春になるとここぞとばかり伸びまくる。2週間おきぐらいに芝刈りをしないと、庭は雑草に占拠されてしまう。雑草だけではなく黄色いタンポポや白くて小さなヒナギクの花も一面に庭をおおう。庭は緑と黄色と白の絨毯(じゅうたん)のようになり、そこに立つと何だか自分が花畑の中の「アルプスの少女ハイジ」にでもなったような気分になる。
タンポポとヒナギクはそっとしておいて雑草だけ刈ってほしいと思うのだが、こちらではこれらの花も雑草扱いですぐ刈られてしまう。そしてその後に似たような野草の花を植えるのだから何だか納得がいかない。(c)asahi.com
自転車だって庭の一部だ!?
ワシも、
そういう年になったということか・・・
スッチーに頭をなでられ、
さらに、また来てね♥!!!と言われ、
下半身が固まった・・・
そのスッチーは、
若いか年増かは忘れたが、
JALだったので、年増であったことは想像に難くない。
(c)オフィスひこうき
こ、これは・・・
病み付きになるらしい。
エエなぁ、これ
もちろんH9型カルディナ2.0Gも最高やけど・・・
一度聞き始めると、ハマります。(c)asahi.com
「うちのリスナーには古きよき礼儀正しさがある」
と話す道上洋三=大阪市北区の朝日放送で
今春放送30年目を迎えたABCラジオ(大阪市)の人気長寿番組がある。平日午前6時半にスタートする「おはようパーソナリティ道上洋三です」。タイトル通り番組の「顔」として、朝の2時間半、リスナーに語りかけてきた道上アナは「最初は30年やるなんて考えてもみなかったけど、リスナーとのつながりを感じ続けた毎日だった」と振り返る。
番組は77年3月にスタートした。朝刊からのニュースの紹介から、筋金入りの阪神タイガースファンとしての野球解説まで話題は幅広い。9代目のアシスタント秋吉英美との息の合った掛け合いも聞きどころだ。
昨年12月の関西圏ラジオ聴取率調査(ビデオリサーチ)によると、ウイークデーの同時間帯に放送された番組の中でトップ。30年で40回近く開いている公開放送には、最近は平均3500人のファンが集い、朝の人気番組として定着している。
道上にとって、ラジオの魅力は「どんな難しい話題をしても、数日後にはリスナーから必ず反応がある。これは珍しいと思う情報を仕入れて話しても、既に生活レベルで知っているリスナーがいる」こと。例えば100年以上前のぬか床を使っている料理人の話をしたら、「うちのは150年以上前のものや」と返ってきた。
インターネットが普及し、携帯電話でテレビも見られる時代。「最近、世間からラジオは面白いと思われてないふしがあるけど、何年も聴き続けて、僕が間違ってたら正してくれるリスナーに支えられてる、すごい世界やと言いたい」
20年を区切りに番組を降りるつもりだったが、95年の阪神大震災で気が変わった。現地で被災者に「道上さんの声聞いた時、今までの生活が戻ってきた気がした」と言われ、自分の声が流れているだけでもいい、声が出る限り番組を続けようと決めた。
情報の送り手として興味がある媒体はミニFMという。寝台特急「出雲」が廃止された時、あるミニFM局が駅からの中継や駅長へのインタビューなどを伝えていた。その緊迫感、臨場感。一つのニュースをきめこまかく取材し、ミニFMならではの小回りを利かせた放送に仕上がっていた。「音の世界の魅力を再認識させてもらった」
「政治、経済、社会、音楽、芸能と、月刊誌みたいに話題を広げすぎた」反省から、これからはシンプルな番組づくりを目指すという。「そして、一人でも多くの人にラジオを聴いてもらいたい」
番組では来年3月まで1年間にわたり、30年にちなんで30の企画を立ち上げる「30番勝負」を展開する。30年を記録した写真集を作るほか、道上自身が和太鼓や作詞作曲に挑戦したり、リスナーから「30」にまつわるエピソードを募集したり、盛りだくさんの内容になる予定だ。
「子供たちの反抗期が遅くなっている」という話を、ある中高一貫校の先生から聞きました。
肉体面での成長は早くなっているのに、精神面では中学生は小学生と大差なく、高校生になってやっと反抗期を迎えることが多い。そして、大人になりたがらず、何でも自分の思い通りにならないとすねるような子供たちが増えている、というのです。
昔の中学生は、学生服の胸ポケットに万年筆を差し、電車代が2倍になっただけで、背伸びしつつも大人の自覚を持ったものです。そういえば、万年筆を使っている中学生を見かけませんね。