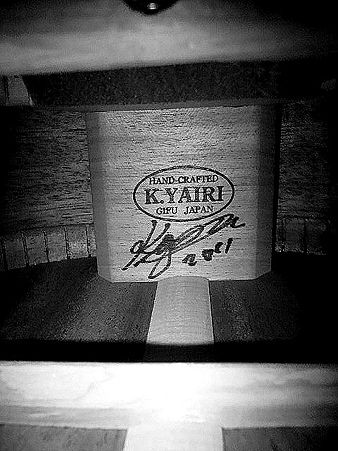【“梅田地下帝国”】迷わず歩くキミは大阪人やワタクシメ、
オーサカジンちゃうけど、迷わずに歩けます。
三番街からWhity、ディアモール、ドーチカ、エトラトセ。
でも確かに、不慣れな人にとってはまさにワケワカランチンのミステリィゾーンやと思うけど。
ほれ。
雉
15年前、東京から転勤してきた私は、歓迎会をしてくれるという大学の先輩とJR大阪駅で待ち合わせた。大阪暮らしが長い先輩は、地下街をぐんぐん進む。1階分エスカレーターで上がったり、薄暗い通路を通ったり。どこを歩いているかもわからない私に、先輩が言った。「この地下を自在に歩けるようになったら、一人前の大阪人」
◇
大阪・梅田の地下には、広大な別世界がある。人呼んで“梅田地下帝国”。阪急三番街から堂島までの南北約1.2キロ、泉の広場から西梅田のオオサカガーデンシティーまでの東西約1.2キロの一帯に、「ホワイティうめだ」「ディアモール大阪」「ドージマ地下センター」の3地下街が広がる。地下はJRの大阪と北新地、阪急、阪神の梅田、地下鉄の梅田、東梅田、西梅田の各駅に通じ、駅前第1~4ビルや阪急、阪神両百貨店、沿道のビル群とも結ぶ。数え上げただけで、頭がクラクラだ。
“帝国”の歴史は、1963年開業のウメダ地下センターから。後発の地下街やビルは別会社なうえ、東から西へ傾斜した地形のせいで地階床面の深さが少しずつ違い、同一平面で連絡できない場所が生じて複雑な構造に。斜めに交差する地上道路に沿って地下通路も斜めなので、初心者には難度が高い。
作家の堀晃(ほり・あきら)さん(65)は、ここを舞台にSF「梅田地下オデッセイ」(78年)を書いた。人々が地下街に突然閉じこめられる、ちょっと怖い物語。人工的に管理された巨大な消費空間で、シャッター一つで密閉される点が「さまよう巨大宇宙船」を思わせ、創作意欲を刺激されたという。近作「笑う闇」(08年)でも、開業が近い「北ヤード」も織り込んで再び“帝国”を取り上げた。「成り行き的な拡大が巨大迷路の面白さを生み、闇市の屋台を取り込んだ路地の雰囲気もある。新しく明るい地下街よりずうっと魅力的」
◇
とはいえ1日240万人が通行する公共空間。「迷宮」なんて評価は返上したいと、鉄道会社や地下街管理会社、行政などが連絡会を結成。事業者ごとにバラバラだった案内表示を統一、共通マップを作成。さらに通路の南北方向にアルファベット、東西方向に数字を割り振り、その組み合わせですべての地上出口に統一的な番号をつけた。設計会社などの研究会も、床材や照度の工夫で迷わず歩ける街路づくりを検討中だ。
今では地下を縦横に歩ける私。思い出は尽きないが、この春、転勤で大阪を離れる。これからこの街はどう姿を変えていくのだろう。サラバ、愛(いと)しの “帝国”――。(織井優佳)

■推薦
画家 マツモトヨーコさん
「世界一のクモの巣」
京都に住んでいた20年ほど前、アルバイト先の大阪・西天満の画廊まで毎日通いました。雨の日は傘を差すのが嫌で、阪急の改札口から地下をどこまで行けるか試行錯誤しました。「泉の広場」経由なども歩いた結果、東梅田方向の最南端のビル地階を東側に抜け、お初天神通りで地上に出る経路に落ち着きました。後日、後輩に披露して「うわ、けものみちや~」と感心されました。疲れている帰りは、階段を避けてエスカレーターをフル活用する別ルート。おなかが痛くなった時にさっと入れるトイレの位置も頭に入れてました。どこまでもつながっていて熟練するとすごく便利だけど、京都の知人は「息ができない!」と恐ろしがっていましたね。
旅先の外国で地下街があったのはソウルぐらい。欧米にはほとんどない。東京も名古屋も、地下街は大きいけど構造はわかりやすい。クモかシロアリの巣みたいに次々つながってここまで広がった地下帝国は、日本一どころか世界一。大阪で新生活を始める人は、とにかく歩き倒してマスターしましょう。

〈略歴〉 58年、大阪府生まれ。京都市立芸術大大学院修了。本紙連載をまとめた著書「偏愛京都」など。