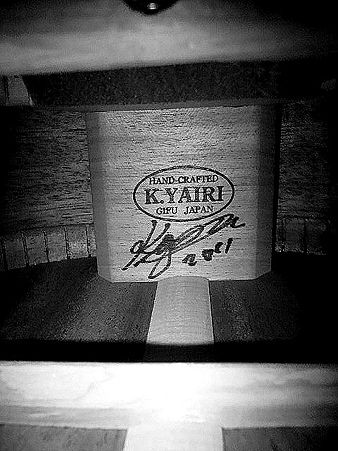×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
最近、神奈川県の小学5年生の女の子から次のような手紙をもらいました。このシリーズは毎週欠かさず読んではいるのだが、
「先生の長い寿命はすごいなと思いました。私も日野原先生のように長生きしてみたいと思うのです。でも長生きしすぎると寂しくなると思いました。なぜかというと、周りの友だちが、それなりの年でみんな死んでしまったら1人残されてしまい、寂しくなると思います」
女の子は「十歳のきみへ」と題した私の本を読んで手紙をくれたようです。いのちは目には見えないが、君のもっている時間、それが君たちのいのちであり、長生きして自分の持ち時間を、他人や社会のために使ってほしいという内容の本です。
女の子の手紙は続きます。
「年をとった人はいろいろと進歩していく電気製品とか、その他の器具を使えなくなりそうで、それが心配です」
なんとかわいい発想でしょう。私は紙面を借りて、こう答えたいのです。
新老人の会の会員にもいつも言っていますが、高齢者は小学校などにどんどん出かけて、お年寄りのもつ知恵や技を次の時代を背負う子どもたちに伝えるとよいのです。きっと子どもたちとお年寄りはとてもよい関係を築けるはずです。
そして、子どもたちの世話で忙しいお父さんやお母さんよりも、お年寄りは自由に使える時間をはるかにたくさんもっているものです。だから時間をかけて、新しい電気製品やコンピューターの使い方を習うことも可能なのです。今までやったことがない絵画や音楽に挑戦することだってできます。子どもたちと一緒にサッカーやテニス、野球のゲームを応援するのも楽しいことでしょう。
そんなお年寄りを見ていたら、長生きしてもよいと思えるでしょう、と子どもたちに伝えたいのです。長生きしている姿が、子どもたちにもすばらしく映るように高齢者が行動すれば、子どもたちは日本のよい文化をお年寄りから受け継ぐことができるでしょう。
子どもたちが「あんなお年寄りになりたいな」と思えるような老人になれるよう、大人はますます努力しなくてはならないと思うのです。
寿命が延びるということは、自分の使える時間が多くなるということです。そうした時間を子どもたちのために使ったら、日本はもっとよい方向に変わっていくのではないでしょうか。