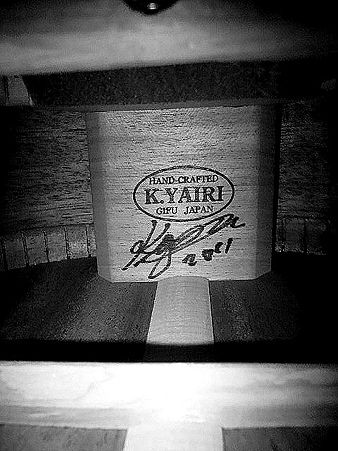×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
犬が年をとるにつれ、人間の認知症に似た「認知障害症候群」の症状が多く表れる一方、飼い主の半数は適切に対処していないことが酪農学園大(江別市)の学生の調査で分かった。治療技術の発達などでペットの高齢化が進む中、終末期のクオリティー・オブ・ライフ(QOL=生活の質)の向上はいま一歩のようだ。う~~~ん、
調査を行ったのは、同大獣医学部六年生の秋田恵里さん(25)。認知障害の実態調査は国内では珍しいといい、結果を九月に札幌市で開かれる「日本小動物獣医学会(北海道)」で発表する。
今年四月から五月にかけて、札幌市内の四カ所の動物病院にアンケート用紙計百二十部を置き、十-十八歳の犬を飼っている七十二人から回答を得た。それによると、「排せつの失敗が増えた」「昼も夜もよくほえるようになった」など認知障害の主な症状七項目のうち、一項目以上が表れていると答えた飼い主は全体の44・4%。犬を年代別に四グループに分け、表れている症状の項目数の平均値を出したところ、最も若い「十、十一歳」が○・四七個だったのに対し、最も高齢の「十六歳以上」は二・七九個と六倍近くになった。
認知障害については「関心が非常にある」と「ある」が計88・9%、「よく知っている」と「知っている」も計61・1%に上った。だが、犬に認知障害の症状や、高齢化による行動の変化が表れていると答えた飼い主のうち、48・6%は治療や予防などの対処をしていなかった。
対処していない理由として、自由記述で「犬は自分の家族であり、何があっても受け入れる」「高齢だから仕方がない」と書いた飼い主が多かった。また、認知障害について知っている人の割合は高かったが、内訳を分析すると、「よく知っている」と答えたのは9・7%と少なく、情報の不足も考えられるという。
秋田さんは「脳の加齢を遅らせる栄養剤を与えたり、介護用品を使用したりと適切に対処すれば、犬のQOLも向上し、飼い主の負担も減る。獣医師が積極的にかかわるべきだと感じた」と話している。