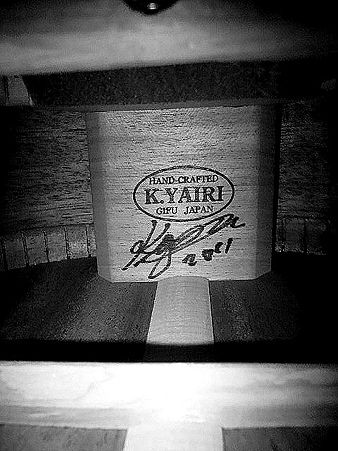×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
死者数が過去最高を更新し、3人に1人の死因となっているがん。患者側から要望の強い痛み緩和治療に、厚生労働省が来年度から本格的に乗り出すことになった。末期はもちろん早期にも起こる痛みを和らげるため、モルヒネなどの使用方法を医師に研修してもらい、患者の相談にのる支援センターを都道府県ごとに設置する。生活の質を保つ大切な治療であるのに、薬物依存を恐れ戸惑う医師も少なくない。患者側の要望に沿う形で、在宅治療の充実にも力を入れる。いいことやと思います。
欧米ではモルヒネなどの医療用麻薬を使った緩和ケアが早くから普及し、末期だけでなく初期のがん患者にも積極的に処方されている。世界保健機関(WHO)も、痛みの程度に応じた使用を勧めている。
厚労省の05年調査では、がんの死者数が32万人を超えて過去最多となり、81年以来、死因のトップとなっている。今後も緩和ケアへの需要が高まることが予想されるが、患者の薬物依存などを恐れ使用をためらう風潮が医師の間で根強い。
05年の製薬会社の調査では、がん治療に携わる医師の10人に1人が、医療用麻薬を痛み止めとして使うことに「ちゅうちょする」と答えた。
このため、がん治療に携わる医師に、早期の患者にも使えるように緩和治療の正しい知識を身につけてもらうため、専用のマニュアルを作るほか、医療用麻薬についても専門医による講習会を各地で開き、使い方などを学んでもらう。患者やその家族を対象にしたシンポジウムなども検討している。
一方、入院せずに通院し、緩和ケアを受けながら自宅での治療を希望する患者も増えている。このため、各都道府県に「在宅緩和ケア支援センター」(仮称)を設置し、医師や看護師が、在宅治療を望む患者や家族の相談に答えて助言をするなど体制作りを急ぐ。
厚労省は、来年度予算の概算要求にセンターの設置費の補助など関連費を盛り込んだ。
〈中川恵一・東大病院緩和ケア診療部長の話〉 日本は医療用麻薬の使用量が米国の20分の1に過ぎず、緩和治療が極端に遅れている。背景には、医師側が根治療法ではないために意識が向かず、対策が後手にまわってきたこともある。今回、厚労省が本格的に対策に乗り出したことは遅すぎた感はあるものの、一歩前進だ。ただ、医師だけでなく、これから医師になる学生に対しての教育こそ必要。文部科学省などとの連携は不十分で、国全体としての取り組みになっていないことは問題だ。