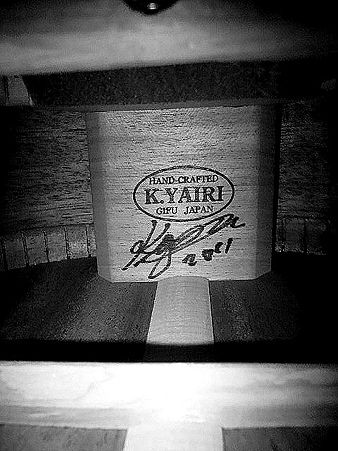×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
現在の医師不足の背景について
医師は通常労働基準法(週40時間勤務)を遵守できない。
病気に夜間や休日はないから。医師の社会的地位が高く、自分の仕事を「聖 職」と考え時間外の無報酬労働をいとわない医師が多かった時代はそれでよかった。
ところが最近は医師は「サービス業の労働者」どみなされ、医療ミスに対しては厳しい制裁がある。そこで割にあわないボランティア仕事を引き受ける人が減った。365日×24時間勤務で、一歩まちがえば被告人という環境なら年収5000万でもなかなか行く人はいない。
数年前、医師臨床研修制度が改革された。
研修を義務化し、報酬を補償し、アルバイトを禁止した。
日本中の病院は研修医を集めるために魅力ある研修プログラムをつくり、他に負けない待遇をアピールするようになった。
もともと医師の研修は丁稚奉公と同じような厳しい修業期間のはず。
それがカタログから選ぶように「給料が良くて楽なところ」に研修医が流れる傾向が出てきた。
研修プログラムも内科、外科、産婦人科、小児科、精神科などを順番に回るようになっているので、「時間外の仕事が多くてきついところ」はすぐバレる。
そこで産婦人科、小児科、麻酔科、救急などが敬遠されるようになった。
一見楽そうな眼科、耳鼻科、皮膚科などが人気が出てきた。
妊娠、分娩、子育てを担当する女性医師の増加もこの傾向に拍車をかけている。
大学病院は一般にスタッフが多くて、医師の待遇は悪い。
診療、教育、研究に魅力があるからそれでも働くのだが、医学部を卒業した後、大学病院での研修を希望する者が減った。
いっぽうで○○医療センターとか○○総合病院とか○○市民病院とかを希望する者が増えた。
どうせ研修するなら地味な地元より都会のブランド病院で、
あるいは逆にスキーのできる北海道で、海のある沖縄でとか考えたりもする。
大学病院はもともと多くの医師をストックして、医局という集団の中で医師の養成(一人前の医師を育て上げるには人手と時間が必要)を行いながら地域医療機関への医師の派遣を行ってきた。
だれも行きたがらないような僻地にはジャンケンでかわりばんこに派遣することができた。
母校の大学病院に勤務する医師が減少していることから、このシステムも壊れつつある。
大学のスタッフさえ欠員なのだから、地域の病院に派遣できるわけがない。
泉佐野の市長のように、掛け持ちでもいいです、週三回でもいいです、となる。
この10〜20年、日本は医学部の定員を減らし続けてきた。
「医師過剰時代」とか言って。医師数が減ると医療費を抑制できる と単純に考えているのでしょう。
しかし高齢化社会、医学の進歩、医療の高度化はむしろこれまでより多数を医師を必要とするようになった。
実際多くの外国では医学部の定員を増やし続けている。
日本では医学部卒業者が減り、女性の比率は増え(卒後数年で家庭に入る人も多い)、
大学病院に勤務する人が減り、きつい科は敬遠され・・・エトセトラで 医師が不足しています。
ほとんどすべては文科省、厚労省の政策ミスの ような気がします。