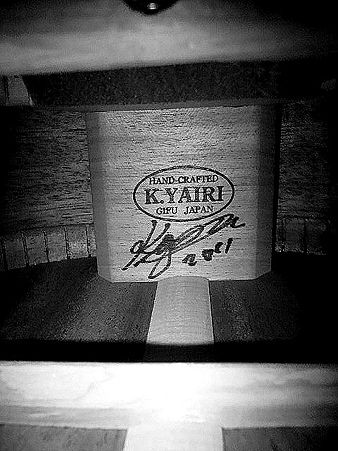【大西直樹教授のキャンパスブログ】ここで何度も取り上げたけど(ホンマか??)、
これは難しい問題。
そこまで神経質になる必要もなかろうと思うが。
英語や他の外国語を必要としない民族(ニッポンジン)、
必要なヒト、やりたいヒトだけやってりゃいいと思う。
現状はまさに、試験でふるい落とすための道具にしか過ぎんのやから。
就学を終えたニッポンジン(=社会人??)で英語を必要とするヒトの割合ってどんなもんでしょう??
1割いってる??
その他いっぱいキャンパスブログ、読み応えあり。
先般、赤塚不二夫氏の追悼文(8月5日の朝日新聞朝刊)の中で、哲学者・鶴見俊輔氏が日本の英語教育にふれている。
「日本の英語教育は、百五十年にわたる政府の投資として失敗した。(中略)戦前でいうと、中学五年、高等学校三年、帝国大学四年をへて英語を書くこともできず、話すこともできず、きくこともできない。(中略)英語はこの長い年月、入学試験で受験生をふるいおとす道具として使われた」
まさに、然(しか)りである。いまだに日本中の大学で、旧態依然とした講読中心の授業がなされている。それも、専任教員が教えるのならまだしも、他大学からの時間講師に任せっきりという現実が一般化している。学生の能力差もおかまいなしだ。
こうした授業では90分1コマで読める英文の量はせいぜい4、5ページにすぎない。通年の30週間で200ページにもならないだろう。単位取得はできても英語の運用能力など身に付かないし、そもそもそれを目的としていない。鶴見氏の発言はこの現状を描ききっている。
国際基督教大(ICU)での英語教育は、専任教員が1クラス20人の学生を相手に課題を何度も与えながら、英語の言語環境を当たり前とする日常を作り出していく。それも1週間8~13コマの単位数で、そのクラスすべてで日本語は使われない。
帰国生や留学生も目立つが、やはり主体は通常の高校出身の学生で、初めから英語の運用が得意な人は実際は多くない。その学生諸君がどう変わるのか。
例えば、リーディングの授業では、いわゆる訳読はまったく行われない。4、5人の小グループをつくり、宿題として読んできた1回30~50ページほどの課題文の内容について英語で論議する。教員はことあるごとに教室を巡り歩いて、クリティカル・シンキング(批判的思考)の重要性を論じ、前提を疑え、論旨を吟味せよ、と討論を導く。
こうしたことを1学期に10週間ずつ3学期を乗り越えたとき、英語に対する恐怖感は消え、自然体で話し発想できる英語力が身に付く。全員がそのレベルに達しないまでも、多くの学生にとって英語が「平気」になっているのは事実である。このため、交換留学先でもその大学の環境に瞬時に順応できる。
言語習得プロセスの苦労を1年間共にした学生たちは、自由にしゃべれなかった時を共通体験として抱くことになる。その克服を経て、生涯続く友情が築かれていく。
それは「幼な友だち」あるいは「戦友」のような感覚ではないだろうか。(国際基督教大教授)
PR